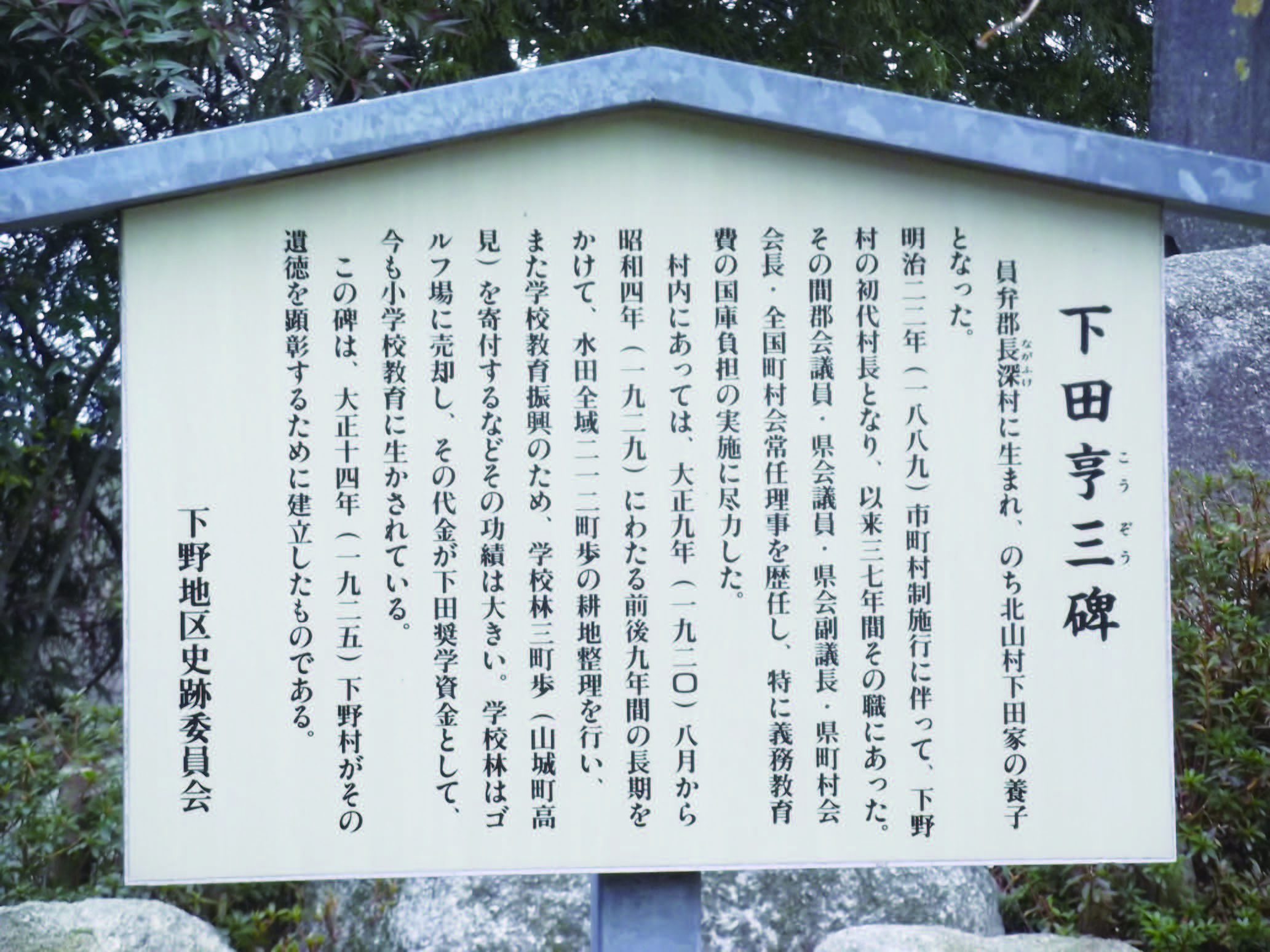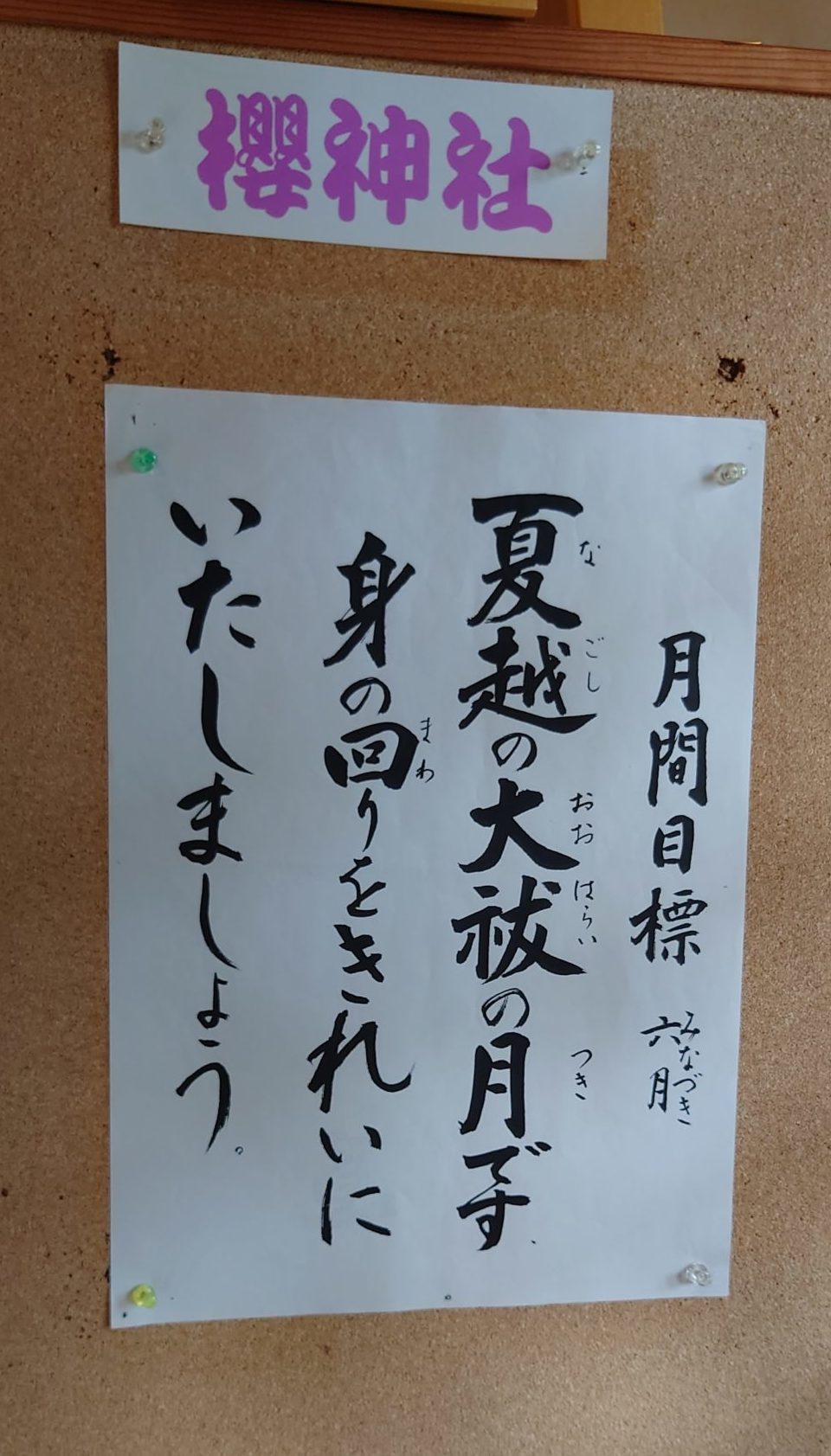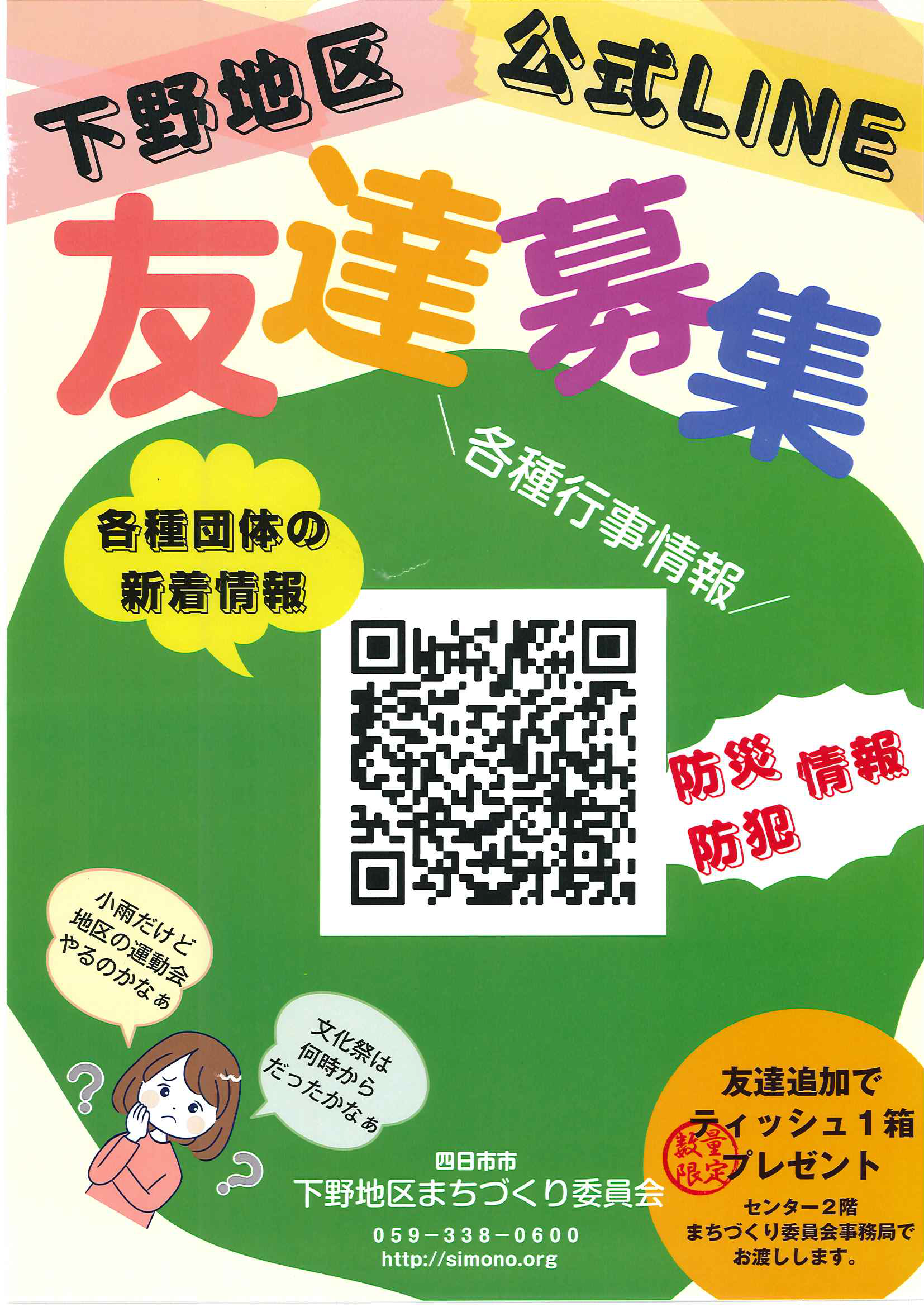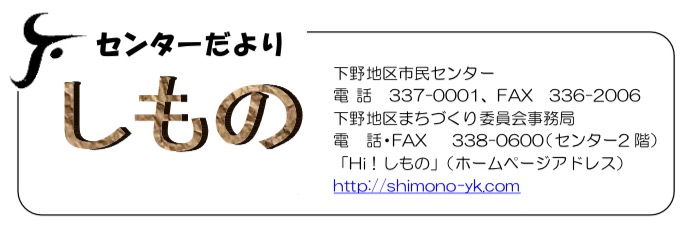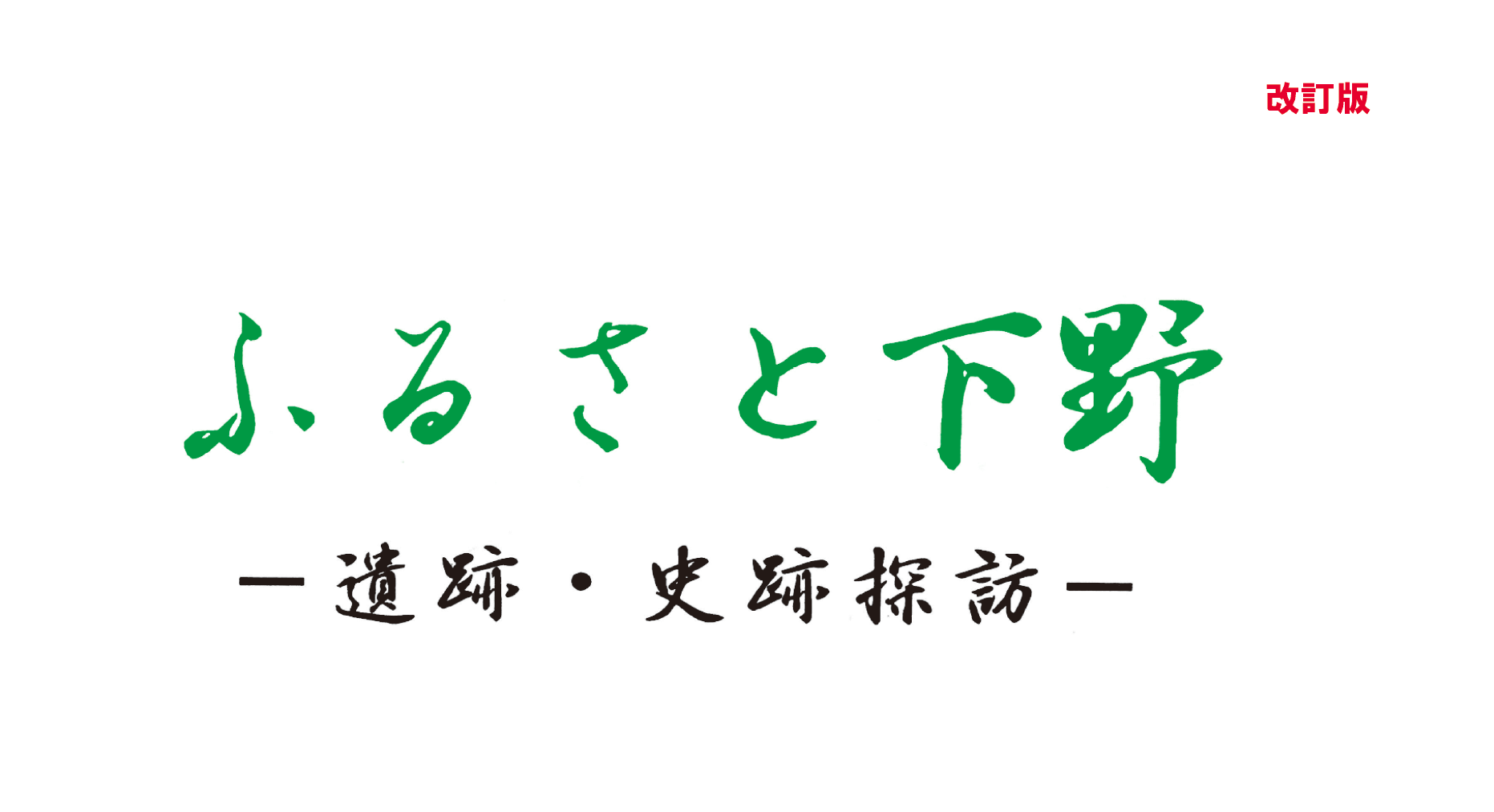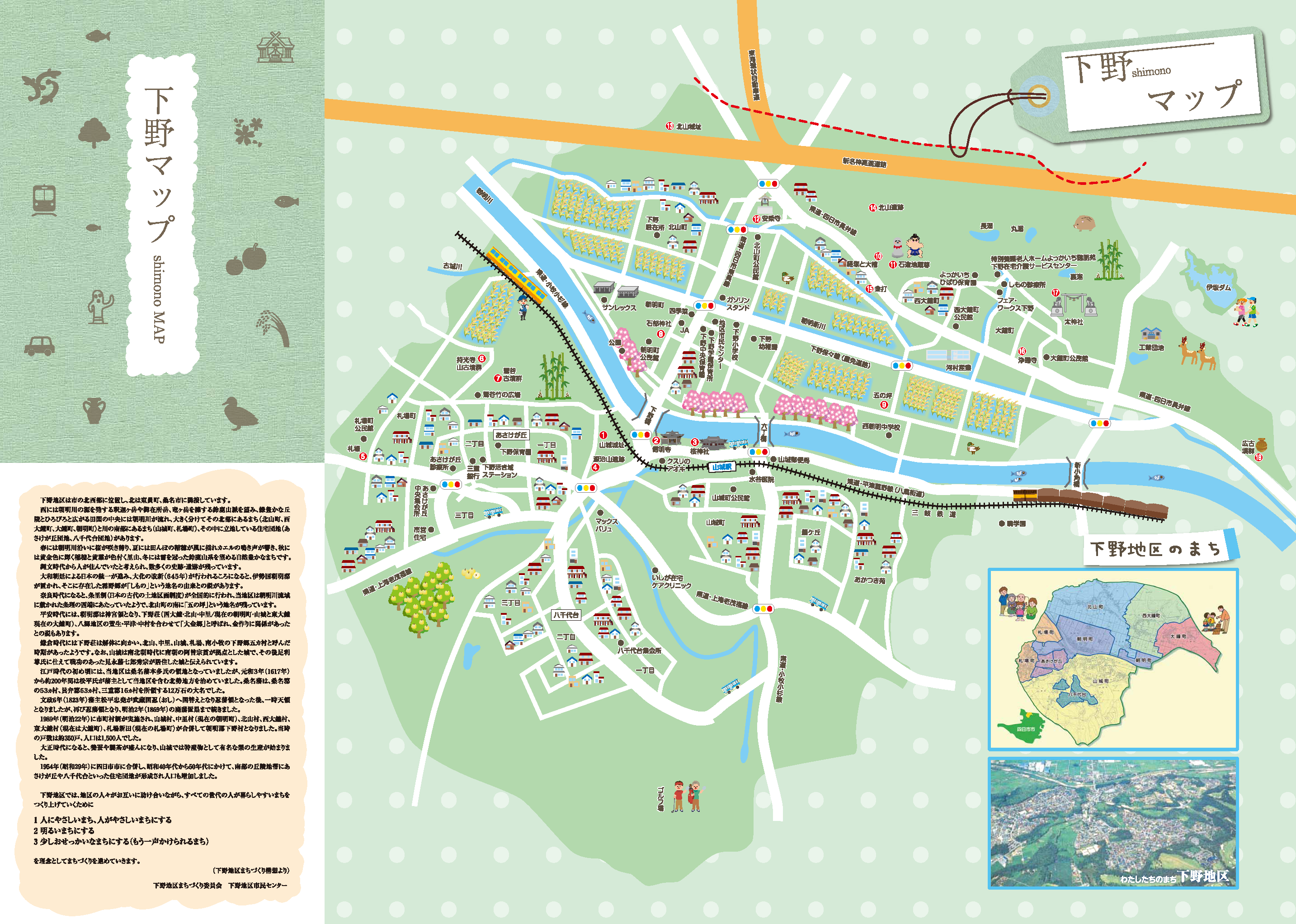江戸時代の下野は、はじめ桑名藩の領地であったが、文政6年(1823)に武蔵国忍藩(埼玉県行田市)領になり、忍藩は代官所(陣屋)を大矢知に置いた。
その頃の農民は、年貢・雑税・課役といった租税に苦しみ、表向きは「四公六民」といわれたが、実際は年貢を納めると収穫物の6割どころか4割も残らなかった。
安政5年(1858)、飢饉が続いて人々は飢えに苦しみ、人心がすさんでゆくのを心配した下野の人たちは、大矢知陣屋に属する庄屋や寺院などの協力を得て、忍藩主松平下総守に願い出てこの地蔵尊を造った。
村人は菰野の八風山中から大みかげ石を運びだし、翌6年(1859) 7月までの1年がかりで地蔵尊は刻まれたという。別名は和合尊とも呼ばれ、今もあがめられている。
また、庄屋たちが忍藩からまけてもらった年貢を取り込み、それを隠すために地蔵堂を建てたとも伝え、この地蔵のことを「あかかくし地蔵」ともいう。




石造地蔵尊